
2024年7月19日 09:00
「飲み会に残業代は出るんですか?」動画について思うこと
「飲み会に残業代は出ますか?」若者はなぜ飲み会に行きたがらないのか
飲み会に誘われた部下が、「残業代は出ますか?」と上司にたずねるショート動画がバズっています。
ネタ動画なのかもしれませんが、部下の言い分は、「自分達は業務上の付き合いなので、そうでないところに時給が発生しないのはおかしい」といった趣旨です。
酒を飲むよりも楽しい娯楽があり、残業代が出ないのなら好きなことに時間を使いたい、とも。
理論的すぎて、反論のしようがない気もします。
「こんな新人嫌だ」「新人の気持ち、わかる」。
ネットの反応は様々ですが、筆者が自分なりに考えてみたところ、ひとつの気づきを得ました。

「飲み会に残業代出ますか?」
実際のやりとりかネタかはわかりませんが、SNSで流れてきたショート動画では、このようなやりとりが繰り広げられます。
部下:社内での飲み会なんですけど、残業代出ますか?
上司:出ないよ。なんで出ると思ったの?
部下:時間外じゃないですか。残業扱いじゃないんですか。
上司:だったら来なくていいよ。
部下:行かなかったみたいな感じになって僕の評価が下がるのはやめてほしいんですけれど。
上司:基本的には業務ではないので、来なくていいです。
これ以降、筆者としては不毛だなと感じる議論が続きます。
いまよく話題に上る「飲み会は強制か」という話ですが、筆者は「金銭ではないけれど何かを支給してもらえた」という気持ちになれるかどうかが全てなのではないかと思っています。

有意義な「飲み」は確かにある
筆者が駆け出し記者だったとき、仕事終わりに先輩と飲む時間はありがたいものでした。一時期は、ある大ニュースの担当をしていたために24時や25時に勤務を終え、そこから閉店の27時まで先輩たちと飲み、翌朝は6時に出社しなければならないことがしょっちゅう、というハードな時期もありましたが、同じプロジェクトの先輩たちと飲むのは有意義だったのです。
その時の筆者は、情報収集などの面で他社の記者より「強い」状況にありました。
マスコミにはどうしても競争意識があります。
そんな中で「常勝」に近く、仕事が終わった後の飲み会は
「よし、この情報を明日特ダネとしてどんなVTRにまとめようか」
「こんどはこんな切り口の質問をしてみたらいいんじゃないか?」
といったワクワクする「作戦会議」の場所でした。
もちろん「よくやった!」という褒め言葉が多く、純粋に嬉しかった記憶があります。
もちろん若いからできていた生活ですし、筆者が駆け出し記者だった頃などもう20年前の話ですから、古い時代の話ではあるかもしれません。
また、別の時には、筆者ら新入社員を先輩が飲みに連れて行ってくれて、印象的な話をしていました。
「自分達は若い時に先輩にたくさん奢ってもらってきたから、今度はあなたたちが自分の後輩にそうしてやってほしい」
ということです。
そんなこともあり、自分が中堅社員になった時には「後輩に還元する」立場です。
同じプロジェクトで頑張ってくれた後輩とたびたびサシ飲みをすることもありました。
ただ、これらの「飲み」が有意義だったなと今思うのには、共通点があります。

部下が主役でいられること
いずれも、仕事の話をしていたということです。それも、たとえ愚痴から始まったとしても、最後は前向きな話で終わります。明日以降、どう「攻め」の仕事をできるか。
筆者は現場の声を聞き(それが想定済みの愚痴だとしても)、同時に自分の経験や知見からアドバイスをし、そんな会話の先に「新しいことをやろう!」「次回はこんな面白いことをやりたいね!」という明確な結論があるのです。
コミュニケーションというよりは、「慰労」「愚痴聞き」「どうやれば面白いことができるか」という起承転結がある場所だったような気がします。
仕事を終えた頃にはお腹も空いていますし、そう言う時は食事をしながらのほうが効率的という考えもあります。
なお、飲みの場では、つねに部下が会話の主体でこそ有意義なものになると筆者は考えます。上司が勝手に喋って気持ちよくなる場所ではありません。部下は飲み屋の店員さんではないのです。
「残業代は出ないけど、美味しいものをタダで食べられたし知識もついた」という場所であれば、また行きたくなるのではないでしょうか。
時給分にはなった、と思えればベストでしょう。
「飲まない」選択肢も
一方で中堅になっていた頃の筆者がいた部署はとにかく勢いが良く、多少遅い時間からでも「みんなで焼肉いくぞー!」ということがしょっちゅうでした。
しかし筆者はこの頃体調を崩していたこともあり、ほとんど参加していませんでした。
翌朝、自分だけが焼き肉を食べていないので周囲の臭い(筆者以外の焼き肉を食べたメンバー同士は感じていません)は割ときついものがありましたが、深夜まで飲んでいても翌朝きちんと仕事をしているメンバーに、逆に尊敬の念を抱いたくらいです。
この焼肉は「慰労」の部分が多く、本当に仕事に関わりのないバカな話で盛り上がっていることも知っていましたし同僚が毎回、前日の飲み会の話をしてくれるので、特に疎外感はありませんでした。
同僚や後輩が、筆者は体調を崩しているので深夜まで飲む体力がなかったことを理解してくれていたのも大きいことです。その理解はありがたく、仕事で返そうと思わせてくれる環境でした。
また、平日はいっさい飲まず、家に帰るか趣味に出かけることを徹底している上司もいました。
実際休日には、趣味の合う部下を自宅に招いたりしていたようですが、誰とも等間隔であると見られるのも、上司としてはひとつの在り方かもしれません。

交流をつくるきっかけの好事例だと思うもの
いずれにせよ、昔ほど気楽に「飲みにいくか?」と声をかけにくくなっている時代なのかもしれません。
しかし、きっかけづくりとして良いなと思うものもあります。
例えば筆者がある企業で見かけたのは、社内にカフェ&バーのスペースがあり、定時をすぎたらそこでビールも飲めるという福利厚生です。
これならハードルは下がりそうです。
また、筆者の取材先では、3か月に1度くらいのペースで会議室でラフな会を開くというものもありました。
これも、時給分を現物支給だと考えてもらえば良いのではないかと思います。
ただし時間は厳守したいものです。ダラダラと続けるものではありません。
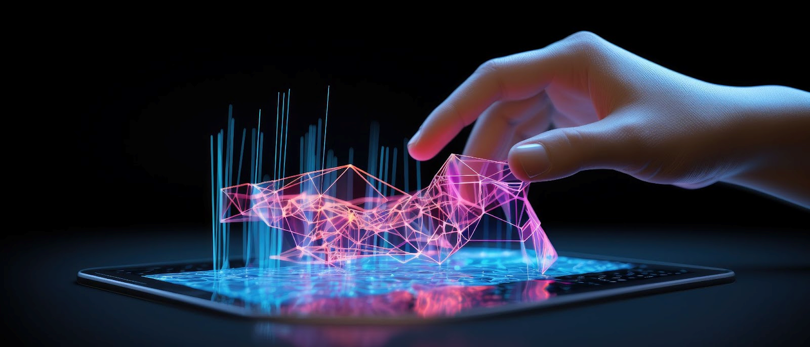
「時代」というよりも「娯楽の進化」の問題ではなかろうか
いかがでしょうか。
「何かを得られた」という実感を与えることができないまま無闇に部下の時間を拘束する。
こうなってしまうと、「残業代払え!」という気持ちになって当然でしょう。ただ話を聞いてほしいだけ、ただ陽気に酒を飲みたいだけ、というのなら、確かにそこに付き合う義務はありません。
なお、現代のこうした考え方は、なにも「時代が殺伐としてきた」というだけではないと筆者は考えます。
今はコスパもタイパも良い娯楽が、自宅にもじゅうぶん溢れています。
外食をしなくてもSNSやオンラインで多くの仲間と交流もできます。そちらのほうが楽なのです。
「お互い定時で帰ってマリオカートやるぞ!21時から1時間限定な!」
そちらのほうが魅力的に映る若者は多いはずです。
社外のリラックスしたところでコミュニケーションを取ろうとするのならば、相手の世代にとっての娯楽に合わせるという発想もまた必要なのではないでしょうか。
コミュニケーションといえば酒だろ!という狭い考え方が会社や上司にあるとしたら、その前提から考え直さなければならないかもしれません。

清水 沙矢香
2002年京都大学理学部卒業後、TBSに主に報道記者として勤務。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種市場・産業など幅広く取材、その後フリー。 取材経験や各種統計の分析を元に多数メディアに寄稿中。



