
2024年7月12日 09:00
設計者とつくり手。立場の異なる2つのプロフェッショナルはどのように共通のゴールに向かうのか。
設計者とつくり手 2つのプロフェッショナルはどのように共通のゴールに向かうのか
現代のものづくりの現場における基本的な構図となっているのが、「設計者」と「つくり手」です。建設業を例にすると、昔は大工の棟梁が木造建築の設計と施工の両方を行っていましたが、今は設計者と施工者が明確に分かれています。
大工の棟梁のように一人ですべてを担当するのであれば衝突することもありません。しかし、設計者とつくり手が分かれている現代においては、同じモノをつくろうとしているにもかかわらず、多くの場面で設計者とつくり手が衝突してしまいます。
では、現代のものづくりの現場において、設計者とつくり手はどのようにして共通のゴールに向かっているのでしょうか。この記事では、建設業でものづくりを行ってきた筆者の経験をもとに、設計者とつくり手のあるべき姿を探っていきたいと思います。

設計者とつくり手
かつての大工の棟梁は、優れたつくり手でありながら、設計・見積もり・資材調達・儀式など、さまざまな業務の指揮をとっていました。*1
スーパーゼネコンのひとつである竹中工務店は、織田信長の普請奉行であった竹中藤兵衛正高を創業者とし、宮大工として伝統建築を手掛けてきた歴史を持ちます。*2
そして、創業から職人が培ってきた意思を「棟梁精神」として受け継ぎ、「工務店」という名前を生み出しました。
工務店とは、「設計と施工とを一貫して請け負うことこそが建築の本来の姿であるという信念」を表す「工務」と、「お客様への奉仕を第一義とすることを示す」ための「店」という言葉を組み合わせた名前です。*3
棟梁の業務範囲や工務店の由来からわかるとおり、昔は「設計」と「施工」は一貫して行われるべきものでした。しかし、近年はそれぞれの分野で専門特化が進み、すべてを一人で担当するのは難しくなっています。
ここでは、現代のものづくりの現場における「設計者」と「つくり手」の役割をみていきましょう。

設計者の役割
設計者の成果物は、「設計図」です。設計図には、製作物の概要、要求性能、仕様、部品の配置、構造などが記載されています。ものづくりの目標は、ユーザーやクライアントが求めるものをつくることであり、そのために必要な情報を設計図にまとめることが、設計者の役割です。
以上のことから、設計者がものづくりに求めることは、設計図どおりに製作を進め、クライアントやユーザーの要望を満足する製作物をつくることだといえます。

つくり手の役割
つくり手の成果物は、「製作物」です。設計図をもとに製作を進め、高品質の製作物をユーザーやクライアントに届けることが、つくり手の役割です。
しかし、設計図の内容によってはそのとおりにつくるのが難しく、品質を担保できないケースもあります。そのような場合に、仕様や性能を満たす範囲で実現可能なデザインやつくり方を提案できるのが、優れたつくり手といえるでしょう。
設計者とつくり手の共通のゴール
ここで留意しておきたいのは、設計者とつくり手は、それぞれの役割がありながらも共通のゴールに向かわなければいけないということです。共通のゴールとは、「クライアントやユーザーが満足する製作物を提供する」ことです。
設計者とつくり手が会社に属している場合、それぞれが会社や部署からの要求に応えるため、役割を全うしようとします。それぞれが課されるデザイン、性能、仕様、コスト、工期などが衝突の原因になります。そのようなときは、クライアントやユーザーが満足する製作物を設計者とつくり手が改めて意識することで、解決に向かうことができるでしょう。
設計者とつくり手の衝突あるある
ここでは、ものづくりの現場でよくみられる「設計者とつくり手の衝突あるある」を紹介します。ものづくりに携わっている方は、共感できるものが多いかもしれません。

「デザイン」と「コスト」
設計者のエゴとつくり手の現実的な意見がぶつかるシーンでありがちなのが、「デザイン」と「コスト」の衝突です。製作物のデザインは重要な要素ではあるものの、クライアントの強い要望がない場合は、性能と比べて説得力に欠ける要素になってしまうことが珍しくありません。
多くのつくり手は、ものづくりが好きであり、デザインにこだわりたいという思いを持っているものです。しかし、優れたデザインを実現するために予算以上のコストが必要になると、難色を示すケースが多いでしょう。
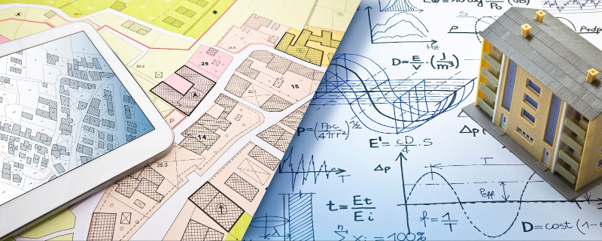
「性能」と「つくりやすさ・安全性」
製作物の性能は、設計者にとって最も守らなければいけない要素のひとつです。基本的に妥協することはできません。しかし、得てして高い性能を実現するには難しい製作工程が必要になるものです。
製作環境によっては難しい製作工程に危険が伴うケースもあります。無理にそのままつくっても、人為的なミスなどにより品質を担保できないかもしれませんし、また、労働災害が発生すればクライアントを巻き込む大きなトラブルに発展します。
無理難題を押し付けて製作ミスや労働災害が生じても、つくり手だけに責任を負わせることはできないでしょう。
設計者が性能を要求するときは、しっかりと実現可能性を検討し、つくりやすさや安全性に配慮した設計を行うことが大切です。

「設計変更」と「工期・納期」
ものづくりの現場においては、設計変更が付きものです。そのときに問題になるのが、工期・納期です。
クライアントやユーザーから追加要望を受けた場合、設計者は要望に応えるべく設計変更を行います。製作が開始している場合、つくり手は工期や納期を守るため、設計変更の資料を発行する期限を厳しく設定するでしょう。
設計者は、プロジェクトをスムーズに進めるため、クライアントやユーザーと良好な関係を築いていきたいものです。そのため、クライアントなどの要望には柔軟に対応したいところですが、つくり手が主張する工期や納期を無視することはできません。しっかりお互いの事情を理解し、現実的な提案をクライアントに行うことが大切です。

設計者とつくり手がともに進むためのポイント
ここまで述べたとおり、設計者とつくり手は、それぞれの役割を全うするために多くの場面で衝突します。それでは、設計者とつくり手は、どのようなことを意識すればともに進めるのでしょうか。ここでは、筆者が感じている大切なポイントを紹介します。
相手の専門分野を学ぶ
まず意識するべきなのが、「相手の専門分野を学ぶ」ということです。相手の主張の背景を知らなければ、理解するのは難しいからです。
昔の大工の棟梁は、設計と施工の両方を行っていました。現代においても、一人の技術者が設計と製作を行うことができれば、衝突することなくさまざまなジレンマを解消できるでしょう。
しかし、専門特化が進んだ現代において、一人ですべてを行うのは現実的ではありません。そのため、相手の専門分野を学び、共通の価値観や言語を持つことが、お互いを理解するうえで大きな助けになります。
相手の専門分野に踏み込んだ高度な提案はできないまでも、相手の言っていることを理解できる程度の知識は、少なくとも身に付けておくとよいでしょう。
最優先事項を見極める
次に挙げるのが、「最優先事項を見極める」ことです。ここで大切なのは、最優先の範囲を自分の専門だけに留めないことです。クライアントやユーザーにとっての最優先事項は、自分の担当範囲外の要素かもしれません。
例えば、設計者が求める「性能」とつくり手が予算を守るために必要な「コスト」が衝突したとします。設計者としては性能が最優先事項ですが、クライアントがコストを優先していることもあります。その場合、クライアントに最低限の性能を確認したうえで、つくり手が安価に調達できる材料を探した方がよいでしょう。
このように、自分の専門に留まらず、常に全体の最優先事項を見極めることが大切です。
クライアント・ユーザーの視点を持つ
設計者とつくり手が「クライアントやユーザーの視点を持つ」ことができれば、多くの場面でベターな選択をすることができます。
筆者は、ものづくりとは、モノをつくることで価値を提供することだと考えています。モノの価値を決めるのは、クライアントやユーザーです。設計者とつくり手の衝突のなかでさまざまな要素が取捨選択されますが、モノを提供されたクライアントやユーザーが喜んでくれれば、そのものづくりは成功といえるでしょう。
クライアントやユーザーの視点でモノの価値を判断しながら、設計者とつくり手が同じ方向に進んでいくことが大切だと考えています。

ものづくりは思いやりが大切
筆者は、設計者とつくり手がものづくりをスムーズに進めるためのポイントは、「相手の専門分野を学ぶ」「最優先事項を見極める」「クライアントの視点を持つ」ことだと考えています。いずれのポイントも「相手」に配慮することが重要です。
相手に配慮すること、つまり、「思いやり」を持つことが、ものづくりで大切な意識といえるでしょう。
<参考>
*1
出所)公益社団法人日本建築士会連合会「大工道具とものづくりの心 第1回 竹中大工道具館が伝えるもの」p.33
https://www.kenchikushikai.or.jp/data/senko/kaishi/KAISHI_201506_DAIKU01.pdf
*2
出所)株式会社竹中工務店「伝統建築」
https://www.takenaka.co.jp/solution/purpose/traditional/index.html
*3
出所)株式会社竹中工務店「竹中のナカにあるモノ」
https://www.takenaka.co.jp/recruit/fresh/about/feature/

オキハラ
1級建築士。 東京大学、同大学院にて建築を学んだのち、株式会社竹中工務店に就職。 構造設計を専門とし、ホテル・事務所・研究所・工場などを設計。 退職後、ライターとしての活動を開始。 建築・不動産をはじめ、幅広いコンテンツで執筆中。



