
2024年6月 7日 09:00
思い入れか、売れ行きか。つくる現場の無限の葛藤
作り手の思い入れが成果物を壊すこともある ものづくりにつきまとう永遠の葛藤を肌で感じた話。
ここではなんども書いていてくどいようですが、筆者はいまCDづくりをしています。
過程でいくつかトラブルも発生し、当初思っていたより時間がかかってしまっているのですが、その場で学んだ、というか気づいたことがあります。
筆者の本業はコラムを書くことであり、それは一種の「ものづくり」です。
曲も同様「ものづくり」です。
しかし、仕事でできていること、これまでも当たり前のようにやってきたことを、音楽の場では完全に忘れてしまっていたのです。

きちんと学んだわけではない世界
はっきり言って筆者は、「作曲」ということについてアカデミックに勉強したことはありません。
ただ、小さい頃に音楽教室で学んだ「なんとなく」のもの、そこからいろんな音楽を聞いてきたという経験があるだけです。「ざっくりこんなものなのかな」と思っていましたし、「音楽なんて自由だろ!」と、たかをくくっていた所もあります。
それでもレコーディングはある程度進んでいったのですが、トラブルが起き、それを引きずってある限界を迎えてしまいました。
「これでは売り物にならない、でもどうしたらいいのかわからない」
業界に人脈もありませんし、困り果てた時ひとりの先輩の存在が浮かんで、お声かけするのも気が引ける相手だとわかりつつ、しかしそこしかなくなりました。
そこで勇気を振り絞って連絡を取りました。
最初は、それは厳しい指摘がありましたが、やりとりをした結果、今あるものを白紙に戻し、アレンジから音源完成まですべてをお願いすることに決めました。
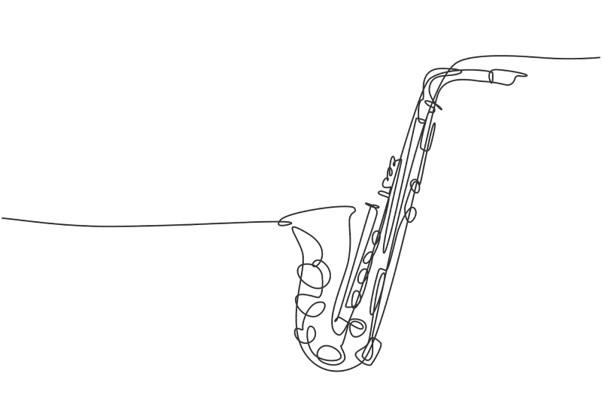
「自由でいいじゃん」ではよくないじゃん?
まず最初に先輩から届いたのが、1曲目のアレンジ音源です。
聴いた感想は、
「こりゃすげえや」
だけでした。
筆者には天邪鬼なところがあり、ちょっとトリッキーなことをしたがる癖があるのですが、その意図も含めて曲を整えてくれていたのです。
ただ1か所、ギターソロの部分だけ、
「もうちょっと高音域がいいな・・・」と思ったので伝えた所、
「追加料金かかるよ?細かなこだわりは脇に置いて、曲全体で掴むようにしろ」
と指導をいただきました。
もちろん聴いている人からすればその8小説の音域がどうのこうのよりも、曲全体として捉えるわけで、それはその通りです。
正直、この注文は筆者の「好み」です。
それでも自分が納得していないものを人様に提供するわけにはいかない、とそこでは思い、ギターソロだけは録り直しをお願いしました。
先輩も「この範囲なら」とすぐに新しいメロディを作って了承してくれました。
そこまでは良かったのですが、では次の曲です。
「音楽なんて自由でいいじゃん。ましてや今回は趣味の世界でやってんだし」
そんな甘い気持ちで作った曲で、確かに一般的な曲の体はなしていないものでした。
それについても、
「これはお前のやりたいことを書いているだけで、曲の形をしてないし、これじゃ聴いてもらえないよ?」
そう言われ、考えたのです。
そうか、ここは考え方を変えなければならない、と。
一番大切なものを忘れていた、ということにも気づきました。

忘れていた、一番大切なもの
確かに今回、これは筆者の趣味の延長というところがあり、そのために製作費をだいぶ自腹で支払ってきました。
ただ、最終的に無料配布するほどの余裕はありません。
1枚でも2枚でも、「売る」つもりでいるわけです。
そう冷静に考えると、自己矛盾に陥っていることがわかりました。
本当にタダで配るならまだしも、このCDをきっかけに自分の音や曲を知ってほしい、という欲望は、正直あるわけです。
であれば、
「聴いてもらう努力」をすべきではないか?
先輩との会話から、それを心の底から感じたのです。
先輩のアドバイスは的確です。
「譜面とか見たところ、考えてることはわかるけれど、あなたは有名人でもなんでもないでしょ?だったら、まず知ってもらうように、そのためには聴きやすさを考えなきゃ」
そうなのです。
不思議なことに、筆者はテレビ局でVTR用の原稿を書いたり、今の仕事をしたりしている中では、伝えたいことがあるのならばまず見てもらう、読んでもらう努力をしなければ、そう考えて仕事をしてきたはずです。
例えばわかりやすい映像を使うことだとか、読みやすい原稿を書くことだとか。
その基本をすっかり忘れていたのです。
「小さなところにこだわりすぎると曲を壊すから、全体で考えろ。いいフレーズを書けてるところもあるんだから」
先輩のその言葉で、忘れていたことを思い出しました。
趣味の延長とはいえ、聴いてほしい気持ちはあるのです。ならば、そういう努力をしなければならないということです。
ちょっとだけ反抗心もあったけれど
その先輩は、名だたるアーティストの曲のアレンジをやってきた人で、「売れ筋」も把握している人です。
失礼ながら筆者は、「理論的に売るみたいな曲作りってどうなん?」とこれまた天邪鬼に考えていました。
しかし、「聴いてほしい」と1ミリでも思っている以上、その理論からは離れられないのです。
どれだけ細かいこだわりを入れ込もうとも、まず人の耳に入らなければ話は始まらない。まさにその通りです。
この人は仕事として音楽をやっているのだから、きちんと流通に乗ることを考えてくれているのです。
しかしこれはこれで、また思ってしまうのです。
どうせ聴く人が詳細まで気にしていないのなら、むしろそこに自分のこだわりを「しれっと」埋め込んでも良いのでは?ということです。
それが小さな自己満足だとしても、自分が納得していないものを聴き手に届けるのは失礼なのでは?
とも思ってしまうのです。
たとえそれが細かすぎて誰にも伝わらないこだわりだったとしても、どこかで満足感を得たい自分もいました。
とはいえ、その「こだわり」が全体との調和を欠いてしまっては全体を壊すことになる、かなり頭はぐるぐるしました。

「誰と作るか」が大切なのかもしれない
さて、このことに関する答えはまだ筆者の中にはありません。
ただ、「こだわり」も良いけれど、「全体との調和を欠いてものを壊す」ようにはなってはいけないかな、というところには納得しています。
では、何を落とし所とするのか。
それは「自分のことをわかってくれる人」との共同作業でこそ満足度が上がるのかもしれません。
自分のこだわりを、他の人の感覚で一度フィルタリングすることで、少し形は変わっても「そう!そういうことをしたかったんだよ!」と頷く形に昇華できればそれはベストです。
「なんだこの始まり方は」と最初は言われた曲も、きちんと意図を伝えれば雰囲気が残り、よりコンパクトになったという先輩のアレンジには感動しました。
「なんだこの始まり方、こんなイントロいるか?いらんだろ。削るぞ」と最初から否定されてしまっていたら、筆者には不満しか残らなかったことでしょう。実際そう言われかけましたが、筆者は意図をしっかりと説明しました。
すると結局はその「こだわり」を理解してもらえたのです。そしてよりカッコよくしてくれたのです。
黙って従っているだけではなく、ちゃんと意図を伝えること、それが素人としての筆者の果たすべきことだと思うようになりました。
きちんと伝える言葉を持ち合わせていることも大事です。いえ、これがなにより大切かもしれません。
しっかりコミュニケーションを取れて、「話が伝わる」人。
ものづくりは一人では完結しない、ということを今、強く肌で感じています。
もちろんいずれは一人で完結できるような知識とスキルがほしいとは思いますが、今の筆者はまだまだその段階にはないようです。

清水 沙矢香
2002年京都大学理学部卒業後、TBSに主に報道記者として勤務。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種市場・産業など幅広く取材、その後フリー。 取材経験や各種統計の分析を元に多数メディアに寄稿中。



