
2024年1月12日 09:00
顧客が「満足」と言ったら、仕事は終わるのか?ものづくりとビジネスのジレンマ
顧客が「満足」と言ったら、仕事は終わるのか?ものづくりとビジネスのジレンマ
今までに出会った職人や芸術家たちには、共通項がありました。
それは、「満足しない」ということ。
顧客から依頼があれば、それに応じて仕事をするのですが、迷いながら仕上げ、キリはありません。
しかしながら、お客様が「満足です」といえば、一区切りを付ける必要がある──。ビジネスでもあるのですから。
この記事では、そんなジレンマとの向き合い方について、考えたいと思います。
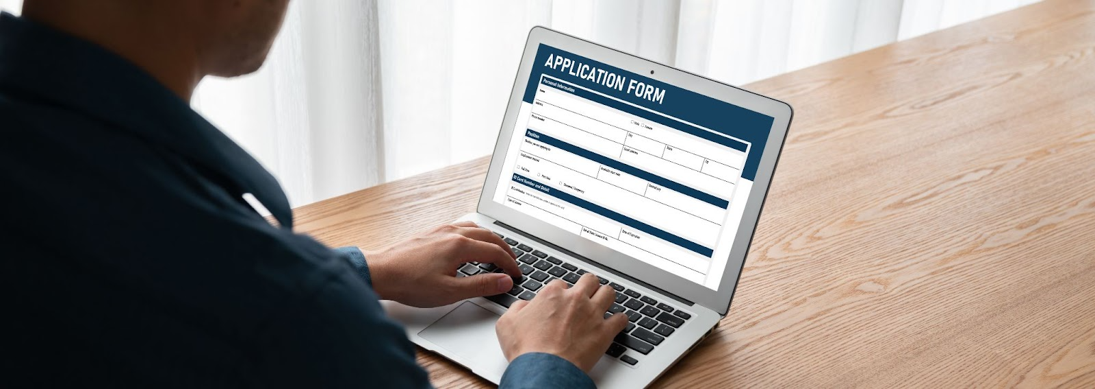
ビジネスにとって重要な顧客満足とは
最初に、「顧客満足」の概念から、確認しておきます。
顧客満足とは何か
顧客満足は、マーケティング用語では「CS(Customer Satisfaction)」といい、顧客が製品・サービスを購入した際、どれだけ満足感を得られたかを測る指標を指します。

CSは、1980年代以降、米国企業を中心として広まっていきました。日本では、日本能率協会が1991年に「CS経営」を提唱したことが知られています。
*1
顧客満足は、その後の顧客行動や口コミ、さらには顧客ロイヤルティ(愛着や信頼)とも密接に関係しており、ビジネスにおいて非常に重要です。
マーケターとしての顧客満足
筆者自身は、企業でマーケティング担当者として、顧客満足と向き合ってきました。
当時、徹底して叩き込まれたのは、「顧客視点」の重要性です。マーケターの自意識がいかに不要で、ときには害悪となるか、理解するところから始まりました。
意思決定のベースとなるのは、「自分がどうしたいか」ではなく、「顧客は何を求めているか」です。
顧客のインサイト(心の奥底にある本音のツボ)を捉え、インサイトに適合した商品・サービスを開発し、顧客に高い満足を提供する──。
満足度の向上によって競合他社より有利なポジションを築き、顧客に選ばれていく、顧客満足競争の渦中にありました。

職人や芸術家の「満足しない」哲学
一方、顧客満足とはまた別の軸にあるのが、職人や芸術家にとっての「満足」です。
筆者は、家業の兼ね合いや、ものづくりに関わる業界での仕事を通じて、職人や芸術家たちのプロフェッショナル性に触れる機会がありました。
自己のこだわりゆえに、顧客とケンカになることさえある彼らに、歯がゆさと尊敬と、そして羨ましさを感じていました。
完璧を求める心は尽きない
職人や芸術家は、顧客が「満足です」と言っても、自分自身は「満足しない」状態を保ちます。
満足の軸が、顧客ではなく自身にあるからです。
自身の美意識や、技術への情熱、さらには作品に込めるメッセージなど、それぞれの強い信念に対し、完璧を求める心は尽きません。
そのうえ、掲げるゴール(理想)は非常に高いものです。100%の自己満足が起きることは、ほぼあり得ません。
「満足しない」哲学とビジネスの狭間
この「満足しない」哲学は、ものづくりの質を高める源泉であると同時に、ビジネス上の課題を生むことがあります。
顧客が「満足」を感じるポイントと、職人や芸術家自身が「満足」を感じるポイントは、しばしば異なるからです。
例を挙げると、職人や芸術家は、技術的な完成度や美的価値に焦点を当てます。
顧客は、自身の感覚とのフィット、あるいは機能性、利便性などに重点を置くケースが多く見られます。
さらに、顧客満足を捉えるうえで重要なのは、
「支払った対価(お金)に対して、満足か・不満か」
が評価されている点です。
顧客は、「価格」という明確な"ものさし"を保有した状態で、満足したり不満を覚えたりしています。
職人や芸術家が、完璧を求める尽きない心で挑む満足度とは、根本的に異なるといえるのです。
このギャップが、ビジネスとしての成功を難しくする原因となります。
答えは簡単ではない
難しいのが、この問題に対する最適解は、ひとつではないことです。
「ビジネスなどは、くだらない」と切り捨て、孤高の道を貫くことで結果的に広く認められる職人もいれば、顧客満足に適応する柔軟性を備えて、多数のファンを獲得する芸術家もいます。
ビジネスとして成功を目指すうえで顧客視点は不可欠ですが、それが"ものづくりの本質"を向上させるかどうかは、また別の問題です。
「お金をとる以上、ビジネス視点を持つべきだ」という意見もあれば、「芸術がオーディエンスに迎合したら、もはやそれは芸術ではない」と主張する人もいます。
「自己満足で商品価値がないものを、作品といえるのか?」と、疑問を投げかける声もあります。

顧客満足と自己満足を融合したものづくり
さまざまな意見と価値観が交錯するなかで、ひとつの答えを見つけ出すのは容易ではありません。
それぞれの立場から見て、信じる選択をしていくしかないでしょう。筆者自身、答えが出ていません。
「満足しない」から生まれる創造と革新
ただ、顧客がどれだけ満足したとしても、作り手が「満足しない」からこそ生まれる、創造と革新の存在を、強く信じています。
「満足していない」という状態が、新しいアイデアやイノベーションの萌芽を生む土壌です。
顧客満足は非常に大切な概念ですが、
「顧客が満足すれば、それでいい」
と捉えれば、これもまた害悪になるリスクがあります。
多様性は新しいチャンスとなり得る
多様性が高まる現代社会では、一昔前のように大衆に迎合するマーケティング戦略は古くなっています。
一人ひとりの多様な顧客に焦点を当てることが重要です。その人たちが求めるオリジナルの価値を提供することで、顧客満足が醸成されます。
別の見方をすると、自己満足と顧客満足が一致する瞬間が増え、ビジネスとしての成功チャンスが広がっているともいえます。
「作り手の個性」と「顧客のニーズ」のマッチングが成功すれば、その結果は、双方にとって幸せなものになるでしょう。
 曲げるところ・曲げないところ
曲げるところ・曲げないところ
柔軟性は重要ですが、すべてにおいて柔軟であるべきではありません。
自分の信念や作品の核心を曲げてしまうと、その作品やものづくりのオリジナリティは失われます。
一方で、顧客のニーズや市場の動きに柔軟に対応したほうが、うまく循環する部分もあります。
このようなバランス感覚が、長期的な成功へと導く鍵といえるでしょう。柔軟性と堅持すべき価値のバランスが、ビジネスの持続性を高めます。
自分が何に価値を見いだしているのか、何に妥協しないと決めているのか。あらためて明確にすることで、顧客もその価値を理解しやすくなります。
相互理解は、顧客との深いつながりを生む土壌となります。理解者に支えられながら、さらなる高みを目指すことができたなら、ものづくりの理想形といえるのではないでしょうか。
さいごに
文中にも書いたとおり、このトピックは、筆者のなかでも結論は出ていません。きっと、複数の回答があるのだと思います。
ものづくりをしていた父は、
「ボツにしたものを、これはすばらしいと言って、高く買っていくんだよ」
と、よく言っていました。心底、ふしぎそうに──。
筆者も創作に関わっていますが、現時点ではビジネスと切り離したところで活動しています。これからも、どう融合していくのがよいのか、考え続けたいテーマです。
注釈
*1
出所)日本能率協会コンサルティング「CS・顧客満足向上コンサルティング」
https://www.jmac.co.jp/consulting/category/marketing/cs.html

三島 つむぎ
ベンチャー企業でマーケティングや組織づくりに従事。商品開発やブランド立ち上げなどの経験を活かしてライターとしても活動中。



