
2023年7月28日 09:00
仕事が楽しくなる?話題のゲーミフィケーションを職場に取り入れる方法
「ゲームが好き」という人は多いですが、仕事とゲームは通常、別のものと考えられています。
ゲームなら何時間も夢中でプレイできるけれど、仕事となるとそうはいかない----、というのが正直なところではないでしょうか。
しかし、もし、ゲームのように楽しく仕事ができたら、従業員一人ひとりの毎日も、組織の生産性も、大きく変わることは、想像に難くありません。
そんな取り組みが「ゲーミフィケーション」です。この記事では、注目度が高まっているゲーミフィケーションについて、取り上げたいと思います。
ゲーミフィケーションとは何か?
まずは「ゲーミフィケーション」とは何か、基本的な事項から確認していきましょう。
ゲーミフィケーションの意味
ゲーミフィケーション(gamification)とは、一言でいえば「ゲーム化」です。
ゲーム設計の要素や思考法を、ゲーム以外の領域に応用することで、まるでゲームのような楽しさを創出しようとする試みを、ゲーミフィケーションといいます。
ユーザーがつい熱中してしまうゲームには、いくつかの特性があります。
【ゲームの特性の例】
・クリアすべき課題があること
・ポイント(経験値など)で経験が可視化されていること
・バッジや勲章をもらえること
・チャレンジすること
・達成すると報酬があること
・競争すること
・仲間と協力すること
これらの要素を、ゲームではないシチュエーションに組み込むことで熱中感が生まれ、タスクの達成が促進されます。

ゲーミフィケーションとマーケティング
ビジネス分野では、ゲーミフィケーションの概念自体は、新しいものではありません。
おもに顧客ロイヤルティ(愛着や信頼、繰り返し購入したい動機づけのある状態)を醸成するための戦略として、活用されてきました。
たとえば、
「商品を購入すると付いてくる点数シールを集めると、プレゼントがもらえる」
といったキャンペーンは、ゲーミフィケーションの一種といえます。
ほかにも、以下の施策は見かける機会が多いものです。
【ゲーミフィケーション施策の例】
・ポイントプログラム:購入金額や来店数などに応じてポイントが貯まる
・会員ランク制度:利用状況に応じて会員をランク分けする
・クイズ:クイズに正解すると特典が得られる
ゲーミフィケーションは、顧客が楽しみながら購入を継続するためのモチベーションとして、効果的に機能します。
職場におけるゲーミフィケーション
一方、近年、注目されているのが、職場におけるゲーミフィケーションです。
職場におけるゲーミフィケーションの目的は、従業員のモチベーションを向上させ、生産性を高めることです。
同じ"仕事"でも、そこに"ゲーム性"があることで、人は熱中する傾向にあります。
具体的な例を挙げると、ゲーム性を多分に含む職業のひとつが「ユーチューバー」です。
・クリアすべき課題:登録者数○○万人達成
・ポイント:再生回数、グッドボタン数
・勲章:銀の盾、金の盾
・競争:他チャンネルとの競争
・報酬:広告収益
上記のように、先ほどご紹介したゲームの特性が、散りばめられています。
私たちが日々取り組む業務にも、ゲームの特性を取り入れると、楽しく夢中になって取り組むことが可能です。
職場に取り入れたいゲーミフィケーションの4要素
「職場にゲーミフィケーションを取り入れてみたい」と思ったら、まずは以下の4要素から検討してみることをおすすめします。
(1)ポイント
(2)バッジ
(3)クエスト
(4)リーダーボード
ひとつずつ、見ていきましょう。

(1)ポイント
ゲームでよく見かけるポイントやスコアと同じように、新しいプロジェクトに挑戦したり、目標を達成したりすると、それに応じてポイントを付与する仕組みを作ります。
売上高などで目標管理を行っているケースは多いと思いますが、それとは別に、行動ベースで日常的に増えるポイントがあると、ゲーム性が増します。
ポイントが増えることで、成長の実感や達成感を、リアルタイムに得られるからです。
【ポイント施策の例】
・プロジェクト完了ポイント:1つのプロジェクトが完了するたびにポイントを付与する
・スキル習得ポイント:新しいスキル習得するたびにポイントを付与する
・感謝ポイント:従業員同士が感謝の気持ちをポイントで贈り合う

(2)バッジ
バッジは、特定の成果を明示的に称えるとともに、社内で共有し、称賛し合えるようにするものです。
【バッジ施策の例】
・無事故バッジ:安全規則を遵守し一定期間、無事故で業務を行った人に付与する
・MVPの表彰:1年または半年といった期間ごとに活躍した人を表彰する
・社内資格制度:社内資格の制度を作り試験合格者などに資格を付与する
・スキルアップ検定:クイズ形式などでスキル習得の学習を行う
参考情報として、厚生労働省が「社内検定認定制度」を実施しています。
【社内検定認定制度とは?】
社内検定認定制度とは、個々の企業や団体が、そこで働く労働者を対象に自主的に行っている検定制度(社内検定)のうち、一定の基準を満たしており、技能振興上奨励すべきであると認めたものを厚生労働大臣が認定する制度です。*1
ゲーミフィケーション施策と連動させながら導入すると、相乗効果が期待できます。
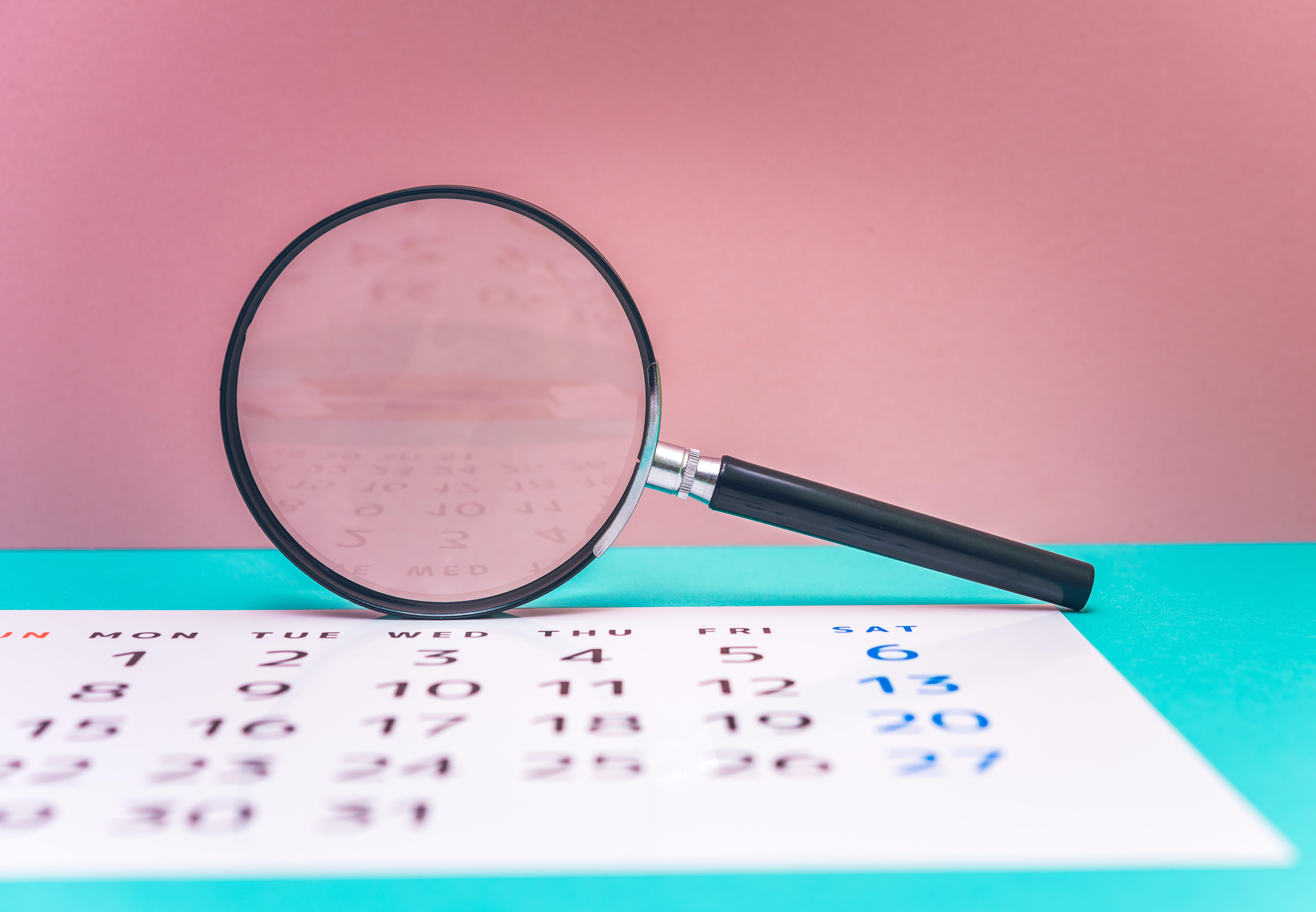
(3)クエスト
ゲーム用語でのクエストは、クリアすべき課題やミッションを指します。たとえば「○○にいる魔物を倒す」「△△のアイテムを入手する」などです。
業務上のタスクをクエストととらえて、クエストを完了するたびに、ポイントやバッジを得られるように設計することで、ゲーム性を強められます。
【クエスト施策の例】
・安全クエスト:一連の安全トレーニングを完了する
・技術向上クエスト:特定の工具や技術の習得を目指す
・チームワーククエスト:特定のプロジェクトをチームで協力して完遂する

(4)リーダーボード
リーダーボードは、スポーツやゲームで使われるランキング表やスコアボードのことです。リアルタイムの成績を開示することが、競争意識を高め、モチベーション向上に役立ちます。
ゲーミフィケーションでは、ポイントやバッジ、クエストの進捗などを、視覚的に表示します。
【リーダーボード施策の例】
・社内SNSや社内報アプリへの掲載
・社内の掲示板への掲示
・定期的なメール配信
たとえば、社内SNSや社内報アプリは、さまざまなIT企業が、簡単に導入できる専用ツールを開発しています。
「いいね」などのリアクション機能のあるツールを採用すると、よりゲーム化を促進できます。
さいごに
本記事では「ゲーミフィケーション」をテーマにお届けしました。
「苦しいことも、ゲームとしてとらえる」
というのは、仕事に限らず、私たちが生きていく知恵ともいえます。
筆者自身、そんな経験がありました。
「ゲーム」と、とらえ直した瞬間、《プレイヤーとしてのもう1人の自分》が生まれ、《苦しい感情の渦に飲み込まれそうな自分》との間に、少しの隙間が生まれました。
その隙間が、渦から自分を引っ張り上げてくれたように感じます。
苦しい時期や仕事も楽しめる自分になれるように、「ゲーミフィケーション」のエッセンスを取り入れていただければと思います。
注釈
*1
出所)厚生労働省「社内検定認定制度」

三島 つむぎ
ベンチャー企業でマーケティングや組織づくりに従事。商品開発やブランド立ち上げなどの経験を活かしてライターとしても活動中。



